人月ビジネスからの脱却

Colony代表の小林が、なぜColonyを創業したのか。
創業までのストーリーを3部に分けてご紹介します。
Colonyの目指すところは何か。
大事にしていることは何か。
ひとつ目は
ソフトにかかる工数への対価ではなく、
ソフトそのものの価値で対価を得ること。
ふたつ目に
常に研究開発企業であること。
つまり、人月ビジネスからの脱却。
今回の記事では、ひとつ目の
『ソフトにかかる工数への対価ではなく、
ソフトそのものの価値で対価を得ること』
について深堀します。
ColonyはDX事業・ソフトウェア開発の会社ですが、
小林は元々ソフトウェア開発の会社に勤めていました。
なぜ独立という道を選んだのか?
それは、ソフトウェア業界における既存システムや、
ビジネスモデルに疑問を感じ、
一石を投じたいという想いから。
T業界には*『人月』と呼ばれる工数管理の単位が存在しています。人月とは、
工数管理をする上で用いられる作業量の単位が『人月(にんげつ)』です。人月は1人が1カ月間働いた場合の作業量を表しシステム開発の見積もりでよく用いられます。「人数×時間(月)」として計算しますので、例えば100人が1カ月働いた場合の作業量は100人月、20人が5カ月働いた場合の作業量も100人月です。さらに発注額を人月で割り、人月単位として単価を確認するのも珍しくありません。
出典:@DIME
業界全体がこのような見積方法というわけではないのですが、ビジネスモデルのひとつとして習慣化している形態です。
上記注釈にもあるように、人月とは発注額を人月で割って出した見積額のことです。
言い換えると、発注を受けた際の報酬は、
システムの中身ではなく、
システムを開発する人件費で報酬が払われる
ということになります。
さらに言い換えると、納品さえしてしまえば
クオリティに関わらず人件費分で企業様に請求されてしまう、ということになります。
もっと言うと、人月の場合、一般的に1ヵ月で終わるような仕事でも、実際に作業する人が3ヵ月かかればその分で計算し、見積もられます。
小林は、このような人月の報酬形態ではなく、
ソフトウェアの価値に対して対価をもらう
『成果報酬型』を取り入れ、
*レベニューシェア型の事業をすべく、
Colonyの立ち上げに至りました。
これが、ソフトにかかる工数への対価ではなく、
ソフトそのものの価値で対価を得ること
を目指す最大の理由です。
レベニューシェアとは契約形態に分類されるもので、主に発注者側と受注者側で利益・リスクを分配しシステム構築や運用を行うモデルです。
レベニュー(revenue)とは「収益」を意味し、シェア(share)は「共有」を意味しています。名称からも、発注者側と受注者側が収益を共有する形態であることがわかります。レベニューシェアは、基本的に分配する収益が明確になりやすいITソリューションやWebサイトの構築などで多く見られる契約形態です。
分配する収益の割合は発注者・受注者で話し合い、事前に決めておきます。
Copyright © 2014 創業手帳 株式会社
これまで慣習となっていた業界の常識(報酬の形態)を大きく変える。
この考えは今の業界にとって非常に挑戦的です。
この挑戦は、会社としてももちろん大きなリスクを伴いますが、何よりお客様ファーストであることを大切にしている創業者の想いなんです。
そのため、冒頭でも触れたように、このようなソフトウェア業界のビジネスモデルに一石を投じ、本当の意味でお客様の力になれるような形態・ソフトウェアを目指して日々試行錯誤しています。
Colony創業物語②へ続く…



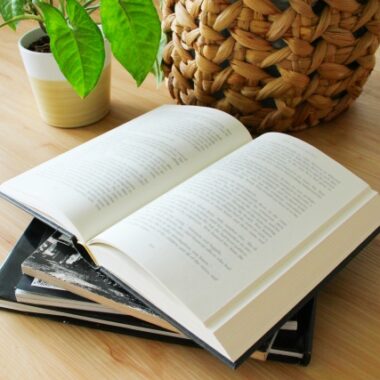
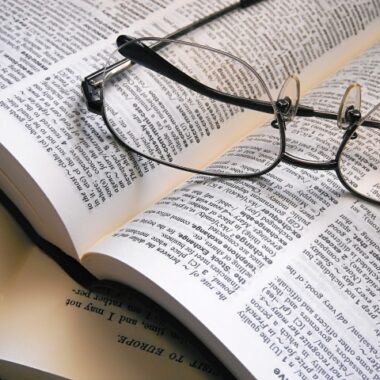

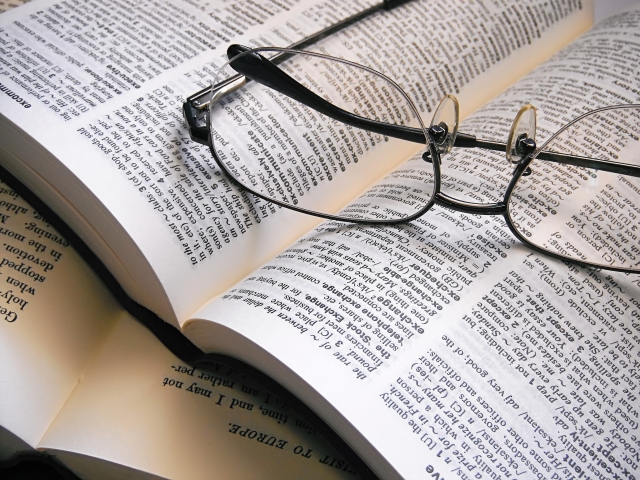


コメント